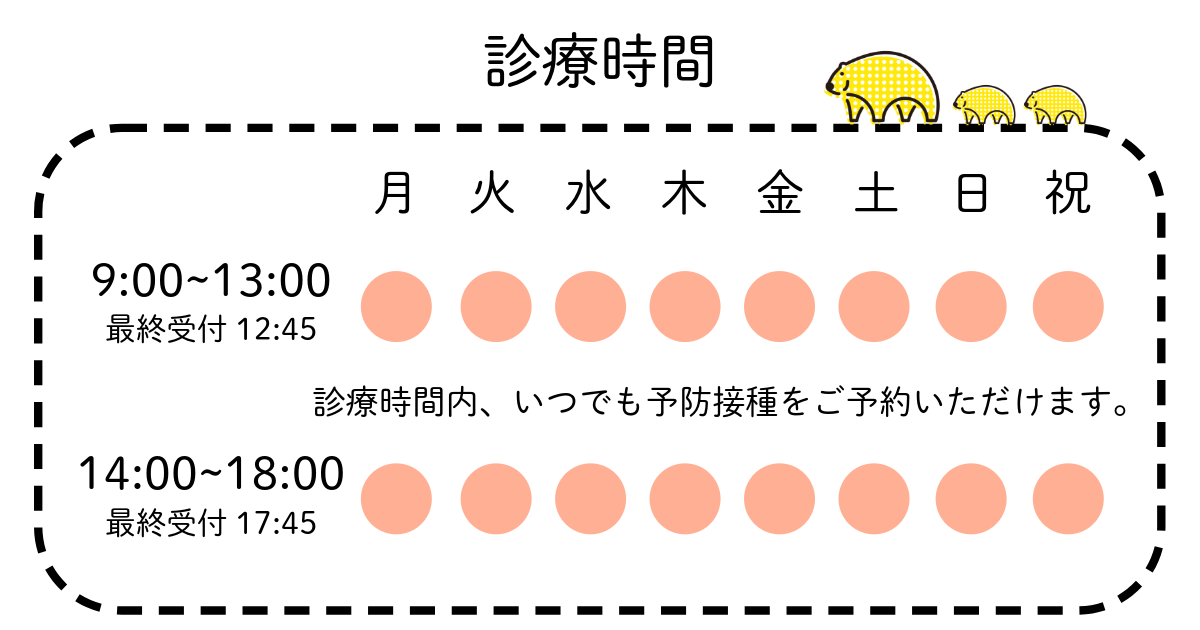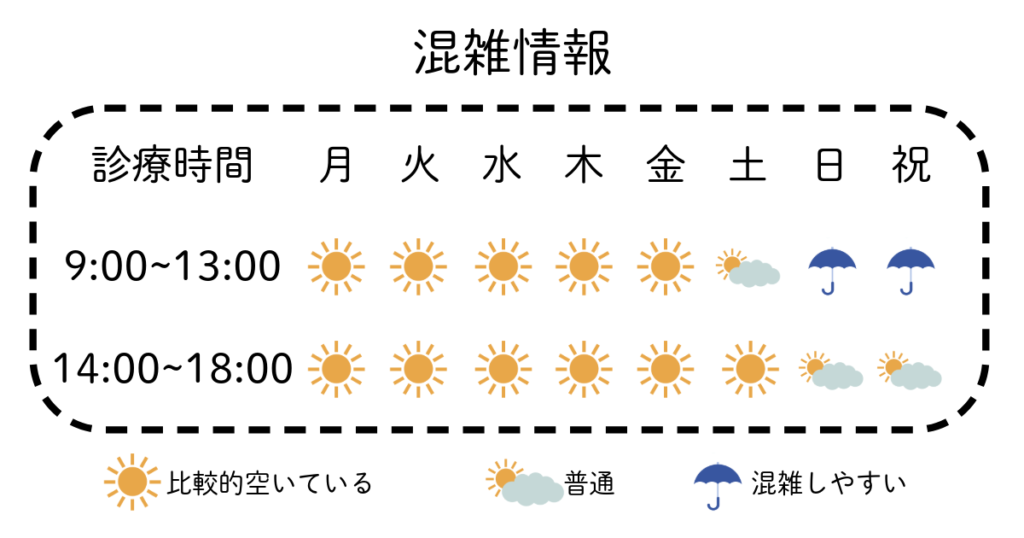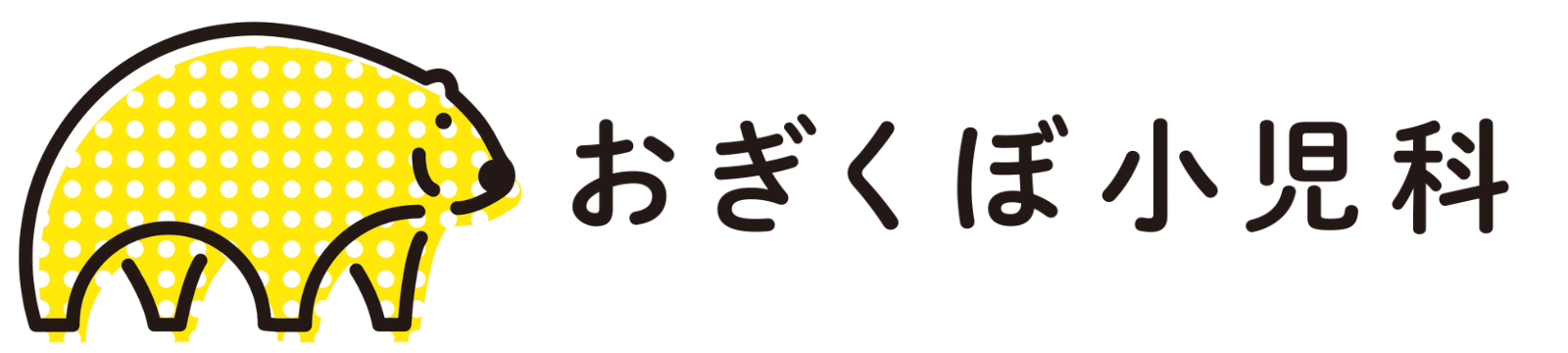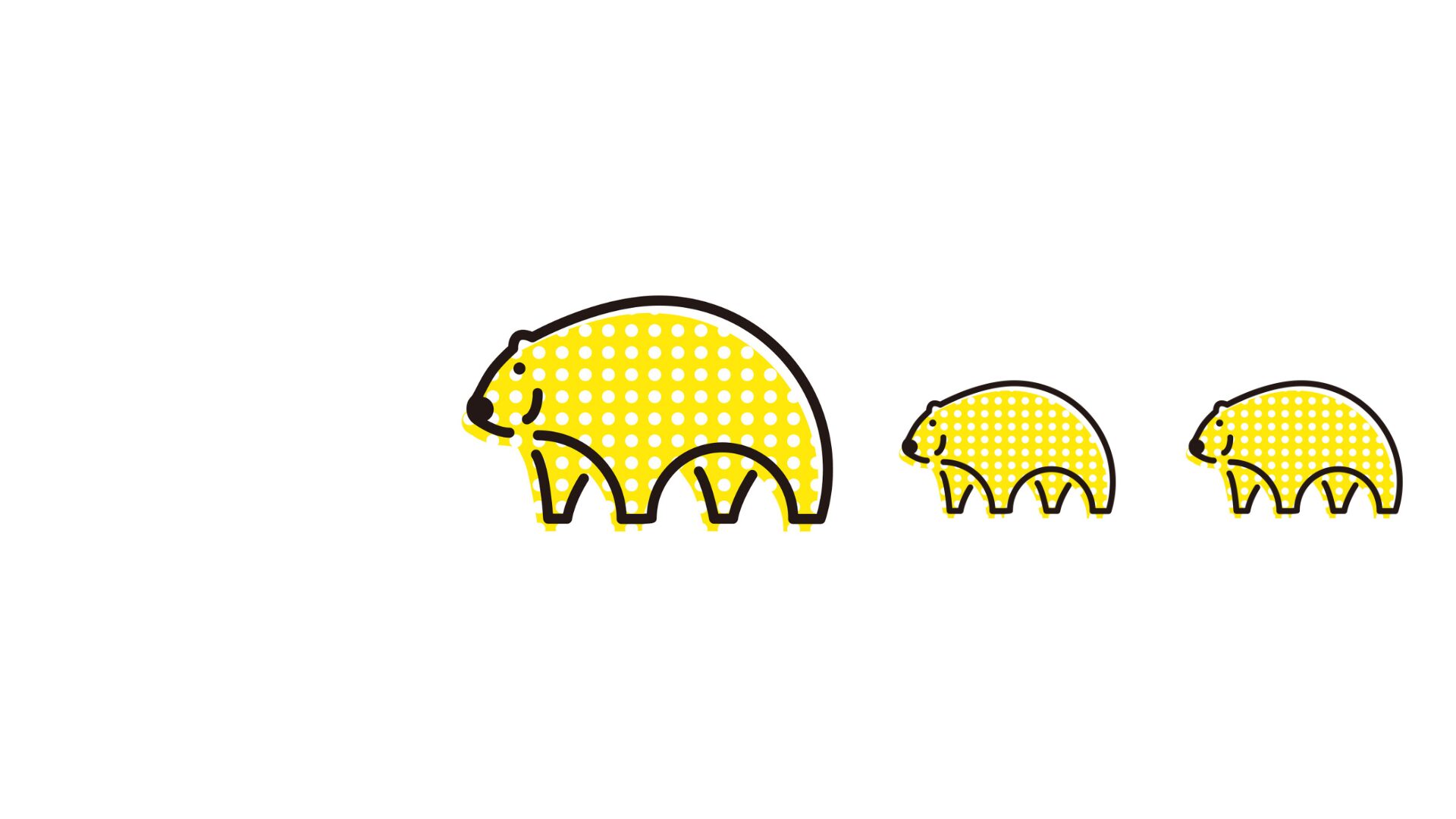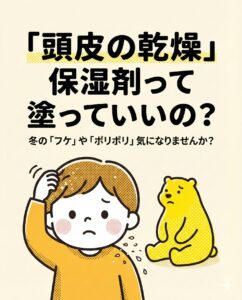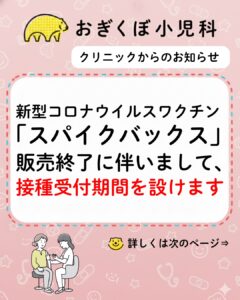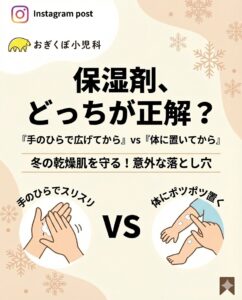子どもの年齢に応じた安全な薬の飲ませ方についてまとめました。シロップ剤や粉薬は乳幼児でも使用されますが、錠剤の服用は原則として学童期(6歳以上)からです。それぞれの年齢段階で、保護者が家庭で役立てられる実用的なコツを紹介します。
・薬は必ず用法用量を守り、正確に計量して飲ませます
・液体の薬は付属のシリンジや計量スプーンを使い、台所用スプーンで測らないでください
・服用の際は子どもをしっかり抱き起こし、誤嚥しない姿勢で与えます
・苦い薬でも「お菓子だよ」とごまかさず、「お薬」であることを伝えましょう
・服用後はコップ1杯の水やお茶などを飲ませて、薬が口に残らないようにします
・子どもが嫌がらずに飲めたときはたくさん褒め、嫌がったときに怒ったり「注射するよ」などと脅したりしないようにしましょう
新生児期(生後1か月未満)
- シロップ剤(液体薬)
- 哺乳瓶の乳首やベビー用のスポイト(シリンジ)を使って、少しずつ口に含ませます。
- 赤ちゃんを横抱きではなく、できるだけ上体を起こした姿勢で支えて与え、誤って気管に入らないように注意します。
- シリンジの場合は赤ちゃんのほおの内側に向けて数滴ずつ落とし、決して喉の奥に一気に注がないでください。
- 飲ませた後は、水やミルクを少量飲ませて、口の中に薬が残らないようにします。
- 粉薬
- 少量の水(1~2滴)で薬をペースト状に練り、清潔な指先で少しずつ赤ちゃんの上あごや頬の内側に塗りつけて飲み込ませます。
- 舌の上に乗せると苦みを感じて吐き出しやすいため、舌を避けるのがコツです。
- 粉薬を水やぬるま湯に溶かしてスポイトで与えても構いませんが、溶かして長時間置くと苦味が増すことがあるため必ず飲む直前に用意します。
注意: 授乳と薬の順番は厳密でなくても大丈夫です。赤ちゃんがお腹いっぱいだと薬を飲まないこともあるので、ミルクの前など空腹時に与えても問題ありません。ミルク(母乳)に直接薬を混ぜることは避けましょう。薬の味でミルクを嫌いになる恐れがあります。
乳児期(生後1か月~1歳)
- シロップ剤
- 基本はそのまま飲ませます。月齢が進んでスプーンに慣れてきたら、小さじスプーンや小さな計量カップで飲ませても良いでしょう。
- 嫌がる場合は無理強いせず、一度に大量に飲ませようとせずに少量ずつ与えます。
- ただし哺乳瓶一杯の飲み物に混ぜると飲みきれず薬効が減るので避けましょう。
- 飲んだ後は白湯やミルクで追い飲みさせ、虫歯予防のため就寝前の服薬では特に口腔内を清潔に保ちます。
- 粉薬
- 新生児期と同様に、水でペースト状にして頬の内側に塗る方法が有効です。
- 生後数か月を過ぎて離乳食が始まったら、アイスクリーム、ジャム、ヨーグルトなど子どもが好きな食べ物ひとさじに薬を混ぜると飲みやすくなることがあります。この場合も必ず一回分ずつ混ぜ、全量を確実に食べさせてください。
- 酸味の強いオレンジジュースやヨーグルトに混ぜると苦みが増す薬もあるため、薬剤師に相談してからにしましょう。
- 粉薬を飲んだ後は、口の中に粉が残らないよう少量の水や麦茶などを飲ませます。
注意: 1歳未満の赤ちゃんにはハチミツ入りの食品は与えないでください。乳児ボツリヌス症の危険があります。
幼児期(1歳~6歳)
- シロップ剤
- この頃になると自我が芽生え、味の好みもはっきりしてくるため、薬を嫌がる子も出てきます。
- 基本はジュースなどに混ぜず、水やお茶で飲む習慣をつけるのが理想です。嫌がる場合は薬の味をごまかす工夫をしましょう。
- 冷たいゼリーやアイスで口を冷やしてから飲ませると苦味を感じにくくなります。
- どうしても飲まない時は、医師に相談し他の風味のシロップ剤がないか確認したり、調剤薬局で調味料シロップを加えてもらうことも検討してください。
- 服用後にはコップ1杯の水や好きな飲み物を飲ませ、後味を和らげると良いでしょう。
- 粉薬
- 粉薬の苦みが苦手な場合は、少量のプリン、チョコクリーム、ジャムなど濃厚で甘い食べ物に混ぜてみます。
- アイスやシャーベットに混ぜて冷たくすると感じにくくなることもあります。
- 市販の服薬補助ゼリーに包んで飲み込ませる方法も有効です。ただし混ぜ込む食品の量はごく少量に留め、確実に全部を食べさせることが大事です。
- ジュースに溶かす場合も、コップ1杯ではなくスプーン数杯程度の少量のジュースに混ぜて飲ませます。
- 飲み物に混ぜるときはストローを使うと一気に飲める子もいます。
注意: 「この野菜ジュースにお薬入れたらおいしくなったよ」などといった誤った説明は避けましょう。大切な食べ物自体を嫌いになる可能性があります。
工夫と声かけ: 幼児期では保護者の態度も重要です。嫌がる子には無理強いせず、なぜ薬を飲む必要があるか優しく説明し(例:「このお薬はお腹の痛いのを治してくれるよ」)、なるべく楽しい雰囲気で飲ませます。子ども自身にスプーンやコップを持たせ、自分で飲ませてみるのも良い方法です。「お薬を全部飲めたらシールを貼ろうね」などご褒美作戦も効果的でしょう。上手に飲めたらしっかり褒めて自信をつけさせ、失敗しても叱らずに励ましてあげてください。
学童期以降(6歳以上)
- シロップ・粉薬
- 学童期になると、自分でコップやスプーンを使って薬を飲めるようになります。用法を子ども本人にも説明し、進んで飲めるよう促しましょう。
- まだ苦手な場合は幼児期と同様にジュースや食品への混和も可能ですが、「全部飲むこと」「少量に混ぜること」の約束を徹底します。
- 学校に薬を持参する必要がある場合は、事前に担任や養護教諭に相談し、飲ませ方やタイミングを決めてください。
- 錠剤
- 6歳頃から徐々に錠剤を飲める子も増えてきます。
- 錠剤を飲ませるときは、必ず子どもを落ち着かせて座らせ、コップ一杯の水またはぬるま湯を用意します。錠剤は舌の上または舌の奥に乗せ、顔を正面に向けたまま水と一緒にゴクっと飲み込みます。うまく飲み込めない場合は、水を含んだ状態で錠剤を口に入れてみたり、ゼリーと一緒に飲み込む方法も試せます。
- 小さいラムネ菓子などで丸飲みの練習をするのも良いでしょう。無理に喉の奥に押し込もうとするとかえって吐き出したり詰まらせたりするので避けます。
注意: 錠剤によっては割ったりすり潰したりしてはいけないものもあります。医師や薬剤師の指示なしに錠剤を砕いて服用させるのはやめましょう。もし錠剤を嫌がる場合は、同じ成分の粉薬やシロップがないか医療者に相談してください。
困ったときは
薬を飲んだ直後に吐いてしまった場合、服用後すぐ(目安として10分以内)であれば落ち着いてからもう一度同じ量を飲ませます。10分以上経ってから吐いた場合は、飲んだ薬の一部が体内に吸収されている可能性があるため追加で飲ませず、次の予定時間まで様子を見ましょう。
まとめ
適切な飲み方で無理せずにお薬を飲みましょう。
また、小児科で処方される薬は「必ず飲まなければ病気が治らない薬」だけではありません。薬が苦手で、飲ませるのが難しい場合は飲まなくても治る薬かどうか、診察時にお聞きください。