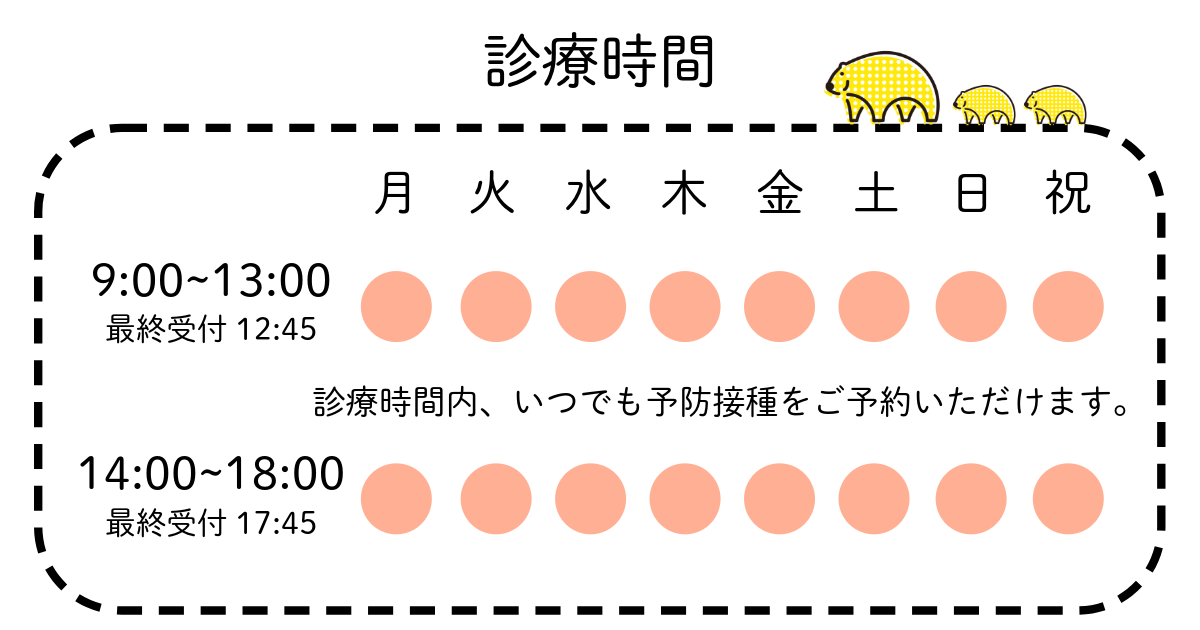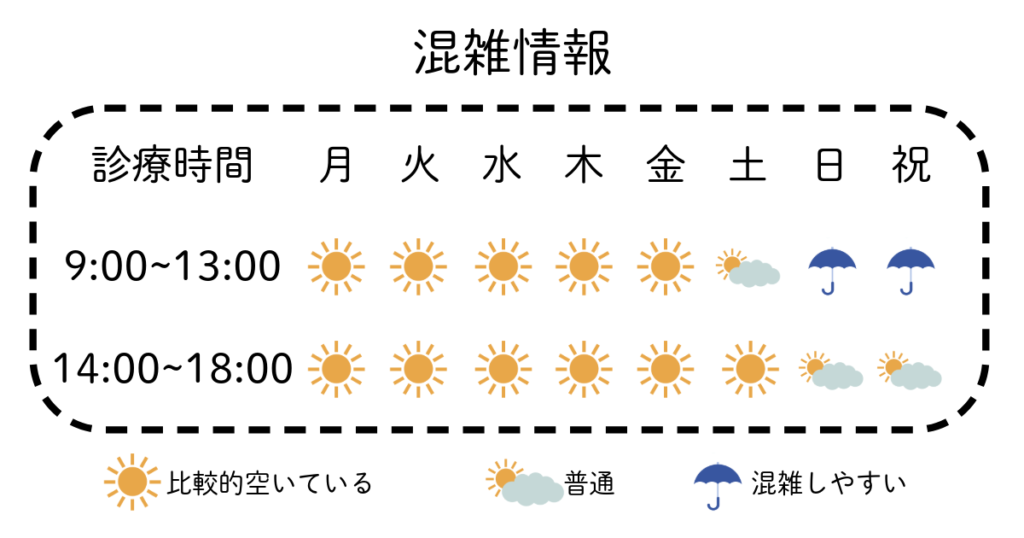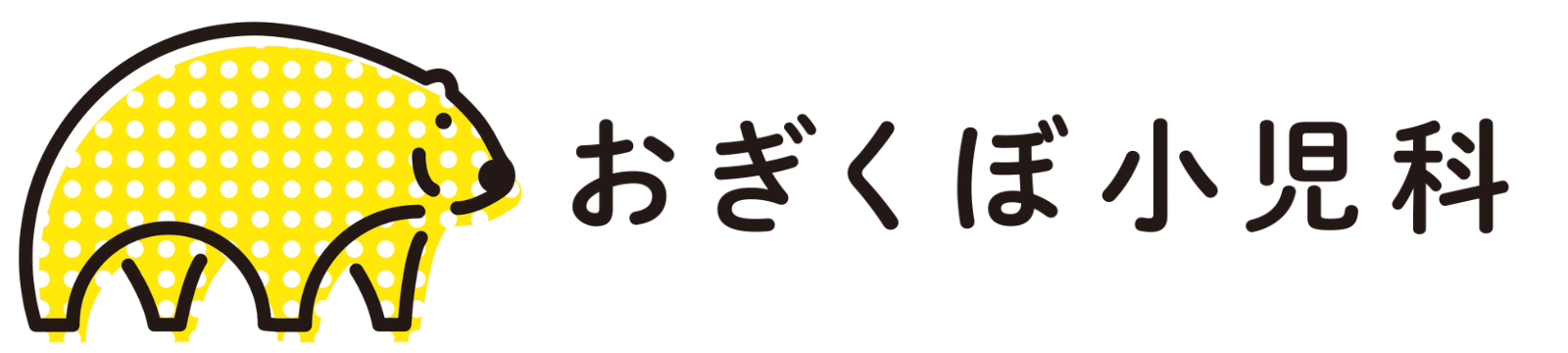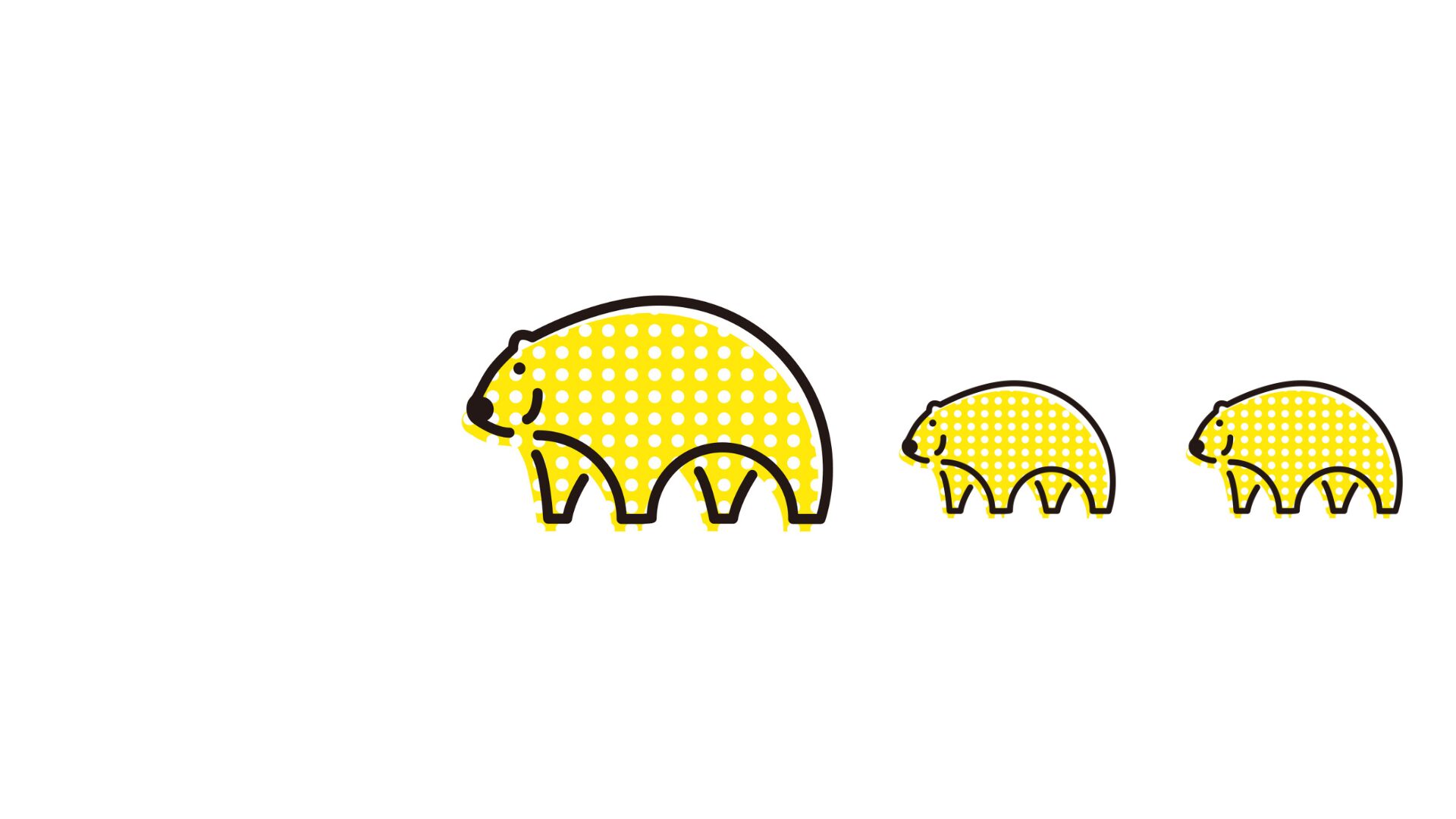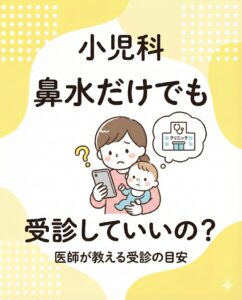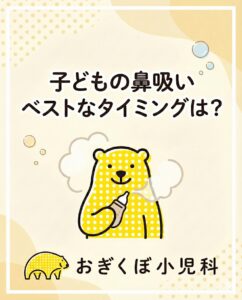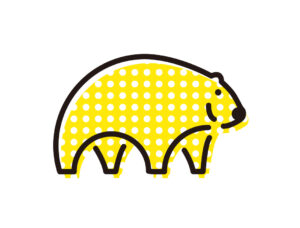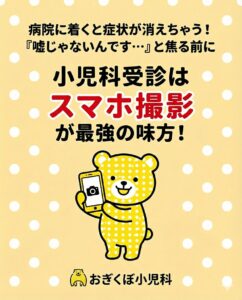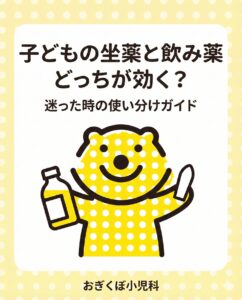夜中に何度も起きる赤ちゃんへの対応は、親にとって大きな問題となりえます。夜の休息が取れないと心身ともに疲弊し、本来楽しいはずの子育ても楽しめなくなってしまいます。こちらの記事では夜泣きについて説明いたします。
夜泣きとは?その原因と発達との関係
「夜泣き」とは、お腹が空いた、オムツが濡れた、体調不良など明確な理由がないのに真夜中(おおよそ深夜0時〜明け方5時頃)に赤ちゃんが泣き出し、あやしてもすぐには泣き止まない状態を指します。生後0〜12か月頃の赤ちゃんには珍しいことではなく、ほとんどすべての赤ちゃんが通る自然な現象です。
新生児期〜生後3ヶ月頃
昼夜の区別がつかず、数時間おきに授乳やおむつ替えが必要なため夜間に起きるのは正常です。
生後4~6ヶ月頃
生後4〜6ヶ月頃から少しずつ夜間まとめて眠れるようになりますが、この頃から周囲の刺激への感受性が高まり、昼間に受けた刺激が夢に出たり、親の顔が見えないと不安になったりして夜泣きすることがあります。
生後7〜9ヶ月頃
生後7〜9ヶ月頃になると人見知りや分離不安が始まり、眠りの途中で親の姿が見えないと不安で泣くケースが増えます。
生後10〜12ヶ月頃
生後10〜12ヶ月頃は身体の発達が進み寝返りやハイハイで寝相が崩れて目覚めたり、日中の新しい経験を消化するため眠りが浅くなることもあります。
このように夜泣きは発達過程の一部であり、一時的なものです(多くの場合、夜泣きは成長とともに自然と落ち着いていきます)。しかし、毎晩の夜泣きに親も疲弊してしまうことがあります。以下では、国内外の小児科ガイドラインや最新の研究にもとづいた効果的な対処法を紹介します。ポイントは、赤ちゃんの生活リズムと睡眠環境を整え、赤ちゃんが「自分で再入眠できる力」を身につけられるよう支えることです。
夜泣きに効果的な対処法(夜間の具体的な対応)
夜中に赤ちゃんが泣き出したとき、焦らず落ち着いて次のようなステップで対応しましょう。
- まず基本的な原因を確認する: 泣いている理由が分からないときは、お腹が空いていないか、おむつが濡れていないかをチェックします。お腹が空いているようなら静かに授乳し、オムツが濡れていれば手早く交換しましょう。体温も触って確認し、暑すぎたり寒すぎたりしないよう調節します(適温は後述)。赤ちゃんの不快な原因を取り除くことで泣き止む場合もあります。
- 夜間は静かで暗い雰囲気を保つ: 授乳やおむつ替えの際も、部屋の照明は暗めにし、刺激を最小限に抑えます。大きな声で話しかけたり遊んだりせず、落ち着いた声で必要最低限のやり取りに留めます。暗い環境は赤ちゃんの体内時計に「夜だよ」と知らせ、再び眠りにつきやすくしてくれます。夜間の対応はできるだけ機械的に、「起きても楽しいことは起きない」と感じさせることがポイントです。
- すぐに抱き上げず、赤ちゃん自身に眠り直すチャンスを与える: 空腹やオムツではない場合、赤ちゃんがぐずっても少し様子を見守り、すぐに抱っこしないようにします。赤ちゃんは睡眠サイクルの中で短い覚醒を挟むことがあり、6ヶ月頃の赤ちゃんなら数分程度ぐずった後に自分でまた寝入るのは正常です。親がすぐ駆けつけないほうが、赤ちゃん自身が泣きやむ力・寝直す力を学ぶことにつながります。実際、米国小児科学会は「泣いてもすぐに反応しすぎないこと」を推奨しており、夜中に少し様子を見ることで赤ちゃんが自分で眠りに戻る力を育むとしています。(healthychildren.org)ただし明らかに激しく泣き続ける場合や、普段と違う泣き方で体調不良が疑われる場合には、無理に放っておかずケアを行ってください。
- 優しく声かけやトントンで安心させる: 赤ちゃんが泣きやめず激しくなるようなら、抱っこは最後の手段として検討します。それまではベッドの中で背中を優しくさすったり、「大丈夫だよ」などと静かに声をかけたりして落ち着かせてみましょう。このときも部屋は暗いまま、赤ちゃんと目を合わせすぎないようにします。親の存在を感じさせつつも刺激は最小限に留め、赤ちゃんが再入眠しやすい雰囲気を保ちます。
- それでもダメなときは抱っこで落ち着かせ、再び寝床へ: トントンや声かけでも泣き止まない場合は、一度抱き上げて落ち着かせても構いません。ただし完全に起こしきってしまわないよう注意しましょう。泣きやんで少し落ち着いたら、赤ちゃんが再びうとうとし始める前にそっと寝床に降ろします。完全に眠ってから置くとまた起きてしまうことが多いため、あくまで「半分寝た状態で置く(後述する「眠りにつく前に寝床へ」の実践)」ことがポイントです。
このような一貫した対応を繰り返すことで、赤ちゃんは「夜中に目覚めても自分でまた寝られるんだ」と学習していきます。実際、最新の研究レビューでも夜泣きへの行動学的介入(いわゆる睡眠トレーニング)により、赤ちゃんと両親双方の睡眠が改善し、赤ちゃんが自分で眠りにつき続けられるようになることが示されています。(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
最初は泣いている赤ちゃんを待つのは心配になるかもしれませんが、赤ちゃんの安全を確認したうえで数分見守ることは発達に悪影響を及ぼすことなく、むしろ睡眠の自立を促す上で有効とされています。
寝かしつけの手順と習慣づくり
夜泣きを減らすためには、寝かしつけの段階から赤ちゃんが自分で眠れる環境と習慣を整えておくことが重要です。以下に、医学的エビデンスに裏付けられた寝かしつけのポイントをまとめます。
決まった寝る前ルーティンを設ける
毎晩寝る前に入浴→授乳(またはミルク)→静かな遊びor絵本→子守歌といった一連の穏やかな流れを作りましょう。乳児期にリラックスできるルーティンを続けることで安心感を与え、寝付きが良くなる効果があります。実際の研究でも、就寝前の一貫したルーティンを導入するだけで入眠までの時間が短縮し、夜間の覚醒回数・時間が減少したとの報告があります。(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
ポイントは毎日同じ順序・同じ時間帯に行い、赤ちゃんに「これをしたら寝る時間」と身体で覚えさせることです。例えば、「夜7時になったらお風呂→マッサージ→授乳→電気を消して子守歌」というパターンを毎日繰り返すと良いでしょう。
眠りにつく前に赤ちゃんを寝床に入れる
寝かしつけの最大のポイントは、赤ちゃんを寝落ちする前、眠そうな状態(うとうと状態)でベッドに置くことです。この「寝入りばなに親の手を借りない」練習によって、赤ちゃんは夜中に目覚めたときも一人で再入眠しやすくなります。反対に、毎回抱っこや授乳で完全に寝入ってからベッドに置いていると、赤ちゃんは「寝るには抱っこ/おっぱいが必要」と認識してしまい、夜中に目覚めた際にもそれを求めて泣き出します。
4ヶ月を過ぎたら少しずつで良いので、授乳や抱っこで眠りに落ちきる前にベッドに置き、寝付く過程を赤ちゃん自身に経験させましょう。
具体的には、赤ちゃんがあくびをしたり目をこすったりし始めたら眠いサインです。そのタイミングでベッドに入れ、部屋を暗くしてあげます。初めは少し泣くかもしれませんが、前述の対応で見守りつつ、自分で寝る練習をさせます。「眠くなったら自分のベッドで寝る」習慣をつけることが、夜泣きを減らす近道です。
授乳と就寝を切り離す
とくに母乳育児の場合、赤ちゃんがおっぱいをくわえたまま眠りに落ちることが多くあります。しかし、毎回それで寝かしつけていると夜間頻繁に起きやすい傾向が報告されています。(pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
生後5〜6ヶ月にもなれば、夜間の栄養要求も徐々に減ってきます。寝る前の授乳はしても構いませんが、授乳で寝落ちしてしまう前に切り上げ、授乳後になにか別のワンクッション(例えば絵本を1冊読むなど)を挟んでから寝かせると良いでしょう。こうすることで「乳首=入眠の道具」という強い関連付けを和らげられます。十分な栄養は日中の授乳や離乳食で摂らせ、夜間は必要最低限の授乳で済むようにすることも、夜通し眠れるようになるコツです。
寝かしつけ方法(睡眠トレーニング)を活用する
夜泣きが続き赤ちゃんもなかなか自力で寝付けない場合、いわゆる「睡眠トレーニング」の手法を取り入れることも検討できます。これは赤ちゃんの寝付きをサポートする行動療法で、さまざまな方法がありますが、代表的なものとして「徐々に泣かせる方法」(Graduated Extinction)があります。これは、赤ちゃんを寝かしつけた後に泣いてもすぐ行かずに一定時間待ち、徐々に待つ時間を延ばしていく方法です。米国小児科学会(AAP)もこの方法を推奨しており、徹底的に泣かせっぱなしにする方法より穏やかで、赤ちゃんが自分で寝付く力を学ぶのに有効とされています。(health.clevelandclinic.orghealth.clevelandclinic.org)
具体的には、例えば最初は2分待ってから様子を見に行き、次は5分、10分…というように段階的に対応までの時間を伸ばしつつ、その間赤ちゃんが自力で寝入るのを促します。もちろん途中で激しく泣き続ける場合には適宜声かけや一時的な抱っこで安心させながら進めます。この方法によって多くの家庭で数日〜1週間程度で夜泣きが改善する報告があります。ただし、こうしたトレーニングの実施には家族の合意と一貫性が大切です。他にも、泣いたら一旦抱き上げて落ち着かせ、また寝かせる「ピックアップ・プットダウン法」や、寝室でそばに椅子を置いて徐々に距離を離す「椅子移動法」など様々なアプローチがあります。(health.clevelandclinic.orghealth.clevelandclinic.org)
いずれの方法も一度で奇跡的に夜泣きがなくなる魔法ではありませんが、基本は「赤ちゃんが一人で眠れるよう親の関与を減らしていく」点で共通しています。(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
ご家庭の方針に合った方法を選び、数週間は根気強く続けることが大切です。科学的なレビューによれば、こうした行動介入は赤ちゃんの睡眠時間を延ばし、親の睡眠の質も向上させる効果が確認されています。(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
家庭でできる工夫:生活リズムと睡眠環境の改善
夜泣きを減らすためには、日中の過ごし方(生活リズム)と夜の睡眠環境を見直すことも有効です。以下に、家庭で実践しやすいポイントを挙げます。
昼夜のメリハリをつける
赤ちゃんに体内時計(サーカディアンリズム)ができてくるのは生後3〜4ヶ月以降です。それまでは難しいですが、それ以降は朝になったらカーテンを開けて日光を浴びさせ、夜は暗く静かに過ごすことで昼と夜の違いを教えていきます。日中は積極的に話しかけたり遊んだりして刺激を与え、適度に赤ちゃんを疲れさせましょう。昼間によく活動した赤ちゃんほど夜ぐっすり眠りやすいことが分かっています。(healthychildren.org)
特に夕方以降は長いお昼寝を避け、適度に起こしておくと夜まとめて寝てくれることがあります。(お昼寝を全くさせないことは逆効果です。適度なお昼寝は取り入れましょう。)
逆に夜中は上述のように刺激を最小限にします。「昼は楽しい時間、夜はつまらない時間」というメリハリが夜泣き対策の基本です。
寝室の環境を整える
赤ちゃんの寝室(または寝る場所)の環境も見直してみましょう。まず室温や寝具の調整です。暑すぎたり寒すぎたりすると眠りが浅くなり泣きやすくなります。理想的な室温は18〜20℃前後、湿度は50〜60%程度とされています。大人には少し涼しいくらいですが、赤ちゃんは体温調節が未熟なためこれくらいが快適です。着せすぎにも注意しましょう。厚着や厚い布団はかえって汗をかかせ不快の原因になります。寒い時期でも重ね着しすぎず、必要に応じて薄手のスリーパー(寝袋型の服)などを使うと良いでしょう。また赤ちゃんは手足で放熱して体温調節しているため、就寝時に靴下は履かせないようにします。足先が冷えているくらいがちょうど良いこともあります。次に照明と音です。就寝前から部屋は照明を落とし、真っ暗が理想です。豆電球程度の薄明かりでも構いませんが、できるだけ暗く静かな環境を用意しましょう。必要であればホワイトノイズ(一定の音、例えばエアコンや換気扇の音のような)や子守歌を流すのも有効です。(health.clevelandclinic.org)テレビやスマホの画面は刺激が強すぎるので寝る前は避けてください。
安全な睡眠姿勢と寝具の確認
赤ちゃんの睡眠の安全も確保しましょう。医学的ガイドラインでは、生後1年までは仰向けで寝かせることが推奨されています。(healthychildren.org)うつ伏せ寝は窒息や乳幼児突然死症候群<SIDS>のリスクになります。また、固くて平らな寝具(ベビー用マットレス)を使い、枕や厚い掛け布団、ぬいぐるみ等は寝床に入れないようにします。(jpeds.or.jpjpeds.or.jp)
これらは窒息の危険があるだけでなく、赤ちゃんが寝返りした際に目を覚ましやすくなる原因にもなります。理想的には赤ちゃんはベビーベッドやベビー布団で一人で寝かせ、ベッドの柵や周囲にクッション等も置かないことが安全かつ快適です。(jpeds.or.jp)なお、夜間の授乳や安心感のために親と同じ部屋で寝る(同室就寝)こと自体は勧められていますが(少なくとも生後6ヶ月までは推奨)、親と同じベッドで寝る(同床就寝)は避けましょう。大人用ベッドは柔らかく窒息リスクがあり、また大人が寝返りで押し潰す事故も報告されています。どうしても添い寝をする場合は安全ガイドラインに沿った環境を整える必要がありますが、基本は「同じ部屋、別の寝床」が安全で質の良い睡眠にも繋がります。
家族で協力し、親の休息も確保する
夜泣き対応が長引くと、どうしてもママやパパに負担が集中しがちです。睡眠不足の蓄積は育児不安や産後うつの一因にもなりえます。(nature.com)科学的研究でも、赤ちゃんの睡眠問題に介入して改善を図ることで母親の睡眠の質が向上し、気分の落ち込みが軽減したとの報告があります(nature.com)無理をしすぎないよう、ぜひパートナーや家族と交代で夜起きる当番を決める、週末に数時間でもまとめて眠らせてもらう、など工夫してみましょう。また、昼間赤ちゃんが寝ている間に一緒に仮眠をとるのも有効です。親が心身ともに余裕を持つことは、結果的に夜泣き対応の質を上げ、赤ちゃんの安心にもつながります。
まとめ
最後に「夜泣きは永遠に続くものではない」ことを覚えておいてください。個人差はありますが、多くの赤ちゃんは1歳を過ぎる頃には夜通し眠れるようになり、夜泣きも落ち着いてきます。それまでは本資料のような対処法を取り入れつつ、赤ちゃんの成長をあたたかく見守ってあげてください。それでも「どうしても改善しない」「家族が極度に参ってしまっている」場合や、「もしかしてどこか具合が悪いのかも?」と不安な場合には、遠慮なく小児科医や助産師に相談しましょう。専門家のアドバイスやサポートを得ることで、適切な睡眠指導や必要に応じて医療的ケアを受けることもできます。夜泣きに悩むのはあなただけではありません。周囲のサポートも得ながら、無理せず乗り切っていきましょう。